『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』を観た。前作から5年、シリーズ第2作がついに公開(劇場公開日:2026年1月30日)。結論から言うと、これは「日本人がつくれる洋画」という言葉を、さらに一歩進めた作品だった。実写にしか見えない背景美術、身体感のあるカメラ、そしてアニメだからこそ成立するキャラクターの存在感。この組み合わせが、かなりのところまで“アニメという器”を突き破ってくる。

ただし、本作は万人に優しい映画ではない。固有名詞は容赦なく飛び交うし、前作を観ていないと置いていかれる場面も多い。さらに言えば、原作小説や宇宙世紀の知識があるほど深く刺さる。そこは覚悟が必要だ。でも、だからこそ刺さる人にはとことん刺さるし、今の時代にハサウェイの物語をぶつける意味がはっきり感じられた。
目次
「逆襲のシャア」という重力の井戸
本作の中心にあるのは、ハサウェイという青年の葛藤だ。かつての戦争で負った傷、革命への信念、そしてテロという手段の是非。彼は連邦政府の腐敗を正すために「マフティー・ナビーユ・エリン」として高官暗殺を続けるが、それは成功が約束された道ではない。むしろ敗北が確定している革命に、彼はあえて身を投じていく。
なぜそんな道を選ぶのか。そこにあるのは、かつての英雄たち――アムロとシャアの影だ。『逆襲のシャア』という巨大な物語が、ハサウェイを縛り続ける。作中には、その重力をあからさまに感じさせる台詞や場面も出てくる。ファンであれば痺れるが、同時に「ハサウェイの物語として見た時に本当に必要なのか?」という問いも浮かぶ。ここは賛否が分かれるポイントだと思う。
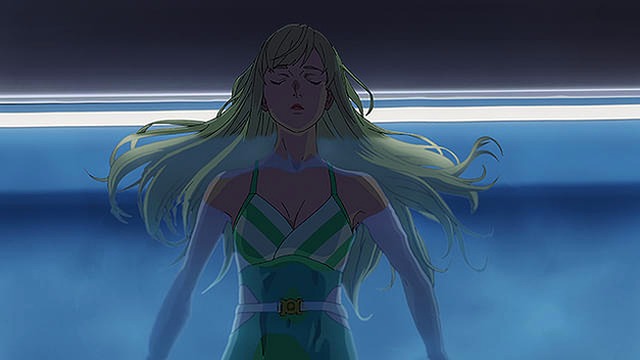
実写的な背景美術が作る「洋画感」
本作の映像は、本当に実写と見紛うほどの説得力がある。海面の光、ガラス越しの反射、湿度のある空気感。これらが積み重なって、アニメーションとは思えない「重さ」が画面に宿る。いわゆる“アニメ的デフォルメ”が強いキャラクターが、この背景の中で浮いてしまいそうなのに、そこが絶妙に調整されているのもすごい。
キャラクターの線はシャープなのに肉感的で、アップになった時の表情は必要以上に誇張しない。背景とキャラのバランスが崩れた瞬間に映画全体の空気が壊れることを、制作陣はよく理解している。その慎重さが、5年という制作期間の重みになっているように感じた。

戦闘シーンの暗さとリアリティ
戦闘シーンは相変わらず圧巻。ただ、暗い。前作でも話題になったが、今回も暗部の描写がかなり強い。これは賛否が分かれると思う。劇場によっては細部が見えにくい可能性もある。ただし、ここには「現実の戦闘は暗い」というリアリティがある。夜明け前の作戦、隠密行動、限られた視界。そういう現実の怖さを、アニメで再現しているとも言える。
モビルスーツの操縦感も強化されていて、トップガン的な恐怖が漂うのが面白い。かつてのガンダムはパイロットの強さやヒーロー性が際立つ戦闘だったが、今回は「人間が巨大兵器を操る怖さ」が前面に出てくる。これはシリーズの中でも独特の味になっている。

ハサウェイとギギの関係性
本作は、革命の物語というよりも、ハサウェイとギギの物語だ。彼らの心の距離が、戦争や政治よりも繊細に描かれている。背景美術のリアルさが、この2人のドラマに“実写映画のような説得力”を与えるのが面白い。青春映画のようでもあり、ロマンティック・コメディのようでもある。戦争を背景にしながら、極めて私的な感情が描かれているのが本作の特徴だ。
ギギというキャラクターも、アニメだから成立するヒロイン像だと思う。現実離れしているのに、妙にリアルに感じる。この「非現実だけど説得力がある」バランスは、アニメーションの強みであり、本作の大きな到達点だと感じた。声の表現も説得力が高く、ギギの存在感がスクリーンに焼き付く。

音響設計が生む没入感
今回は音の設計も特に印象深い。コクピット内の金属音、機体の軋み、エンジンの低い振動。これらが「巨大兵器の中にいる」という身体感を強く与える。映像がリアルだからこそ、音の説得力がさらに増幅している。静かなシーンと爆発的なシーンの落差も大きく、劇場で観る価値がはっきりある作品だと感じた。
映像のゲーム的立体感
今作は、カメラの動きや距離感が“ゲーム的”に感じられる場面が多い。廃墟の拠点を歩くカットでは奥行きがはっきり意識され、視点移動の速度や角度がゲームのプレイ感覚に近い。これは近年の実写作品でも見られる流れで、ビデオゲーム的な表現が映像の文法に取り込まれている証拠だと思う。アニメが実写を目指し、実写がゲームの文法を取り込み、そしてまたアニメに戻ってくる。そんな循環を感じた。
結果として、戦闘の臨場感が一段増している。視点が一定ではなく、時に俯瞰、時にパイロット視点へと切り替わることで、観客は「見ている」だけでなく「体験している」感覚に引きずり込まれる。映画館の大きなスクリーンで観ると、その効果はさらに強い。
前作を観るべき理由
「シリーズものは初見に厳しい」とよく言われるが、本作は特にその傾向が強い。前作の最後から地続きで始まるため、人物関係や政治状況の説明がほとんどない。ハサウェイが何を背負っているのか、ギギがどんな立場の人物なのか、ケネスとの距離感はどうなのか――そうした要素は前作を知っている前提で進む。もし時間が許すなら、前作を復習してから劇場に入ると、没入感がまるで違う。
さらに、小説版に触れていると「どこが変わったのか」「どこをあえて残したのか」が分かり、作り手の意図が見えてくる。これはマニア向けの楽しみ方だが、深く刺さりたい人にはおすすめだ。
シリーズものとしての難しさ
本作は3部作の2作目。単体で理解するのは正直厳しい。前作のラストから直接繋がるので、未見だと話が追えない。さらに、小説版を読んでいると補完できる部分も多い。これはシリーズものが抱える宿命ではあるが、ここまで割り切っているのは珍しい。観る側に高いリテラシーを求める映画だ。
しかし、その割り切りがあるからこそ、映画としての密度が生まれているのも事実だ。説明のための説明を削ぎ落とし、感情と映像の流れに集中させる。ここに「洋画的な大胆さ」を感じる。

「ガンダム」というIPの重さ
物語の終盤には、いわゆる「ガンダムの呪い」に近い重さが漂う。シリーズの歴史が長いからこそ、過去作の引用は観客に強烈に刺さる一方で、ハサウェイ自身の物語が薄れてしまう危険もある。ここは本作の魅力であり、弱点でもある。IPの重さを背負いつつ、新しい物語をどう描くのか。その緊張感が画面から伝わってくる。
個人的には、この重さを引き受けたうえで「次作でどこまで解放されるのか」に期待している。三部作の中盤だからこそ、圧力が強く、息苦しい。その閉塞感が作品の空気になっているのは間違いない。

観終わった後に残るもの
観終わった後に強く残るのは、「希望」と「諦め」が同時に滲む感触だった。革命は成功しないかもしれない。理想は届かないかもしれない。それでも、手を伸ばしてしまう人間の性(さが)を、ハサウェイは背負っている。彼は英雄ではないし、完全な正義でもない。だからこそ、物語の苦さがリアルに響く。
一方で、ギギとの関係や、細部に差し込まれる静かな瞬間には、確かな温度がある。暗い世界の中で、ほんの少しだけ人間らしい光が見える。そのコントラストが、この作品をただの「重い映画」にさせていない。重く、苦く、でもどこか美しい。そんな余韻が残る一本だ。
そして、観終わった後に思うのは「ここからどう終わらせるのか」という一点だ。三部作の中盤として、ここまで息苦しい空気を作り上げた以上、最終作は必ず答えを出さなければならない。その意味で本作は、物語の結末への期待と不安を最大限に膨らませる“中間報告”でもある。続編に向けた助走としては、これ以上ないくらい濃厚だ。
また、映画というよりも「体験」に近い感触が残ったことも書いておきたい。映像の密度、音の圧、暗さの中で細部を追いかける集中力。そのすべてが、劇場という空間でしか味わえない体験になっていた。配信や小さな画面で観ると印象が変わるタイプの作品だからこそ、できるだけ大きなスクリーンで観る価値がある。
最後に一つだけ。ハサウェイという人物は、強い信念を持ちながらも、常に迷い続けている。その迷いがあるからこそ、人間としてのリアリティがあるし、観客の心にも刺さる。完璧な英雄ではなく、欠点も弱さも抱えた青年の物語として見ると、本作はさらに味わい深くなる。
だからこそ、次作でハサウェイがどんな答えを出すのかが最大の見どころだ。今作はその前夜として、胸の奥に静かな火種を残してくれる。
まとめ:アニメだから到達できた“洋画”
『キルケーの魔女』は、ただの続編ではない。日本のアニメが「洋画的な映像体験」を突き詰めた一つの到達点だと思う。実写に寄せるだけではなく、アニメでしかできない表現をきっちり残している。その結果、洋画のようでいて、洋画には絶対にならない独特の空気が生まれている。
派手な展開や分かりやすさを求める人には合わないかもしれない。でも、シリーズに愛がある人、映像表現に興味がある人には間違いなく刺さる。映画館の大きなスクリーンで、ぜひこの空気を体感してほしい。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』
劇場公開日:2026年1月30日
3部作の2作目(原作小説の中巻)



